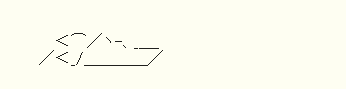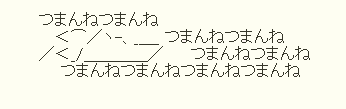木々にさよならを
★目次ページに戻る
雨漏りしていると思われる側に面した和室の天井を見てみます。
そこには何の変化も見られません。
ベランダに出て軒天を見上げてみます。
そちらも何も変わったところはありません。
雨漏りではないのか????
脚立を持ってきて押し入れの上段のベニヤ板を押し上げて屋根裏を覗いてみます。

片手で体を支えて、もう一方の片手で板を押し上げます。
上段の鴨居があるので、逆エビの不自然な体勢が苦しい。
天井裏は当然暗黒の世界。
真っ暗闇が一面に広がっていると思ったら。
ヲイッ!
一番高い位置と思われる場所に、二箇所ほど明かりが漏れてる。Σ(゜д゜;)
写真には写りませんでした。
スレートがずれて隙間が空いているのか、棟包みがずれているのか?
いずれにせよ、そこから辺りから雨水が浸入していると思われます。
懐中電灯を照らして屋根裏を見回します。

ライトに照らし出された屋根裏は想像していたよりもきれいな状態。
でも、よくよく見ると雨漏りが原因だと思われる異常な箇所が幾つか散見できました。

 この柱はリビングと和室の間の鴨居の上で止まっているので、建物全体を支えているメインの柱ではありません。
この柱はリビングと和室の間の鴨居の上で止まっているので、建物全体を支えているメインの柱ではありません。
明かりの漏れている場所の周辺の野地板と、一番高い位置まで伸びている主柱だけが、雨漏りの形跡が顕著に表れています。
他の部分にはあまり水が広がった形跡が無いので、開いている穴は普通の雨降り程度では水が入ってこなくて、吹き込みとか豪雨とかの条件でのみ雨が入って来てるようです。
普通の雨ぐらいで水が入ってくるようならば、こんな程度では済まないと思えるからです。
いずれにせよ早急に修理をしないと、屋根がどんどん劣化していきます。
懐中電灯を更に上方向に向けた時・・・
あ、あれは・・・・!(゚Д゚;)!!

以前見たことがある。
モンスズメバチの巣!!
既にお留守になっているようです。
定期的にバルサンを焚いていたので、私が購入してからではなくて先代オーナさんの時代に作られたような気がします。
他の場所は大丈夫かとカメラを持った手首だけを回してあちらこちら撮影します。
帰って来てから写真を見ていたら、もう1個蜂の巣がありました。
 これはヒメスズメバチの巣と思える。
これはヒメスズメバチの巣と思える。
育児途中で放棄したようだから、近年の巣かな?
隅の方は柱に隠れているし、暗くてよくわかんないのですが、他の場所はこれと言った異常は見当たりませんでした。
で、写真を見ていてふと気付きました。
天井のベニヤ板を持ち上げている真上と後ろは見えないんですよ。
もし、そこにスズメバチの巣があったら・・・
今頃、顔を腫らしてうなっている私がいるかもしれない。∑(´□`;)
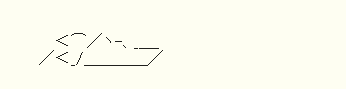
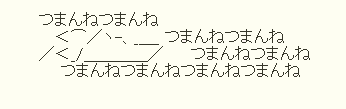
もういいっすよ。 もうやる気ないっすよ。
せっかくバルコニー修理してきたのに。
大金かけたくないから、無い知恵ひねって工夫してたのに。
結局、屋根修理と同時に職人さんに任せることになるかもだなんて・・・。
『正直言うと、築30年、殆ど価値の無いような山の一軒家に、今更数百万ものお金をつぎ込むのもどういう物かな~?って思ってるんですよ。』
↑こんな事書いたもんだからフラグ立っちまった。
もう更新する気失せた。
え?嫌ならやめろって??
おまえのつまらない作文なんか無くってもいいって??
同情を買おうとするオマエの見え透いた魂胆はうんざりだって?
ゴメンナサイ、書きます。
読んでください。
お願いします。 (;´Д`)ノ
雨漏りが発覚したのですぐさま業者に屋根修理の見積もりを出してくれるよう依頼しました。
ですが、現時点でまだ見積金額が出てきません。
業者さんは「忙しくてもう少し待ってくれ」とのこと。
山の家に行く道すがら、リフォームで足場が立っている家が2軒あります。
今年の長雨と多湿はどこの家もダメージを受けたみたいで、修理の依頼が殺到している様子。
台風シーズンも一応過ぎ去ったみたいだし、ここんとこ好天続きですっかり乾燥しちゃってるし、長雨が終われば冬期の乾燥時期がやってくるし。
出来るだけお金をかけないように、ケチケチ内容で見積もりしてくれるよう頼んでますから後回しにされても文句は言えない。(゚∀゚)
今の様子だと修理は冬になりそうな雰囲気。
そんなわけでこちらも急ぐ必要がないのでゆっくり構えてます。
バルコニーは現状復帰すると多額の費用が嵩むのと、また十数年で同じ問題が出てくるので、耐久性重視の構造にする予定です。

抜けるような青空ってこういう空を指すんでしょうね。
今日はメチャ快晴。
出し入れしてきてばちゃばちゃになってる資材道具類を、来るべく大規模修繕に備えて片付けと、足場が組まれる家の周囲の手入れを行います。

天井の梁には水滴跡と水が染みこんだ形跡がくっきりと模様になって表れています。
また長雨が始まるようだと腐食が始まってきます。
壁のベニヤ板が乾燥している時でないと脚立を立てかけられないですからね。
次回に防腐剤挿入をやってみようかと思います。
まだ目に見えるような腐敗の兆候は出ていませんが、この梁の中にはしっかりと腐敗菌が入り込んでいると思います。

出した道具がたくさんあって、テーブルの上とかに放置していたものですから、お片付けにちょっと時間がかかってしまいました。
ベランダに出て補修途中の場所をチェックしてみます。
 クラック1本だったのが2本に増えた。
クラック1本だったのが2本に増えた。
かなり水分を含んでいたんでしょうね。
干割れが大きくなって、今まで存在しなかったクラックが出来ています。
パテ埋め補修した大引き(基礎材)もクラックが大きくなって、エポキシパテにまで亀裂が入っています。

硬化したエポキシってかなり固いんですよ。
ハンマーとたがね使ってかち割るぐらいしないとクラックなんて入りません。
材木の収縮比がとても大きかったということです。
柱のパテ埋め面にもクラックが・・・

材木との密着が甘かったのでしょう。
簡単にクラックが入っちゃいました。
これが大工さん達が
『樹脂での補修をやっても無駄だ。』と言われるゆえんですね。
木の収縮に合わせて何度も何度もこまめに補修していかなければいけません。
手間ばっかりかかってしまいます。
*これらの写真とデータ類は「樹脂による木材補修」のページに、追記データとして記述する予定です。
1番柱基部は腐食部分を削りだした後、防湿のためにペンキを塗っていました。
この柱もデッキ板も乾燥してカチカチになっていますが、もはや強度は望めません。

腐敗菌はおおかた死滅しているはずですが、再び水分が浸透したら柔らかくなってしまいます。
強い衝撃には耐えられないでしょう。

てすりのクラックもひどくなってきました。
今年の多雨多湿はあらゆる所にダメージを残していきました。
家の表に出て周囲にある木々を見つめます。

屋根の上に枝を張っている大きな樫の木。
降り注ぐ落ち葉が屋根にとって良くありません。
切ることになります。
こちらの家に一番近い杉の木。
これも切る予定です。


庭にある病気になったコナラの木。
これも屋根に落ち葉を降り注ぎますので切ります。
そして家の周りを取り囲む小さな樹木達。

足場を組むのに障害になるので切っていきます。
家の修理のために大金をかけることの損失よりも、ここまで大きくなった木たちを切ってしまうことの方がとても悲しい。

たくさんの樹木達にゴメンネと語りかけます。
今までありがとう。
さようなら。
家の玄関前に立ち並ぶ大きな木たちは、電線があったりして私の手では切る事が出来ません。
重機で上を支えながら業者の方が切り倒すことになります。
バルコニーから見下ろす小さな木たちは、私でも切る事が出来るので自分でやります。

細い木、太い木。
障害になりそうな物はチェンソーで切りました。
今回はバルコニー下の半分。
それでも全部合わせると10本以上。
切り倒してバラバラにして、森の中へ積み上げて。
役立ちそうな太い幹は杭や丸太代わりにする予定で、乾燥のために物置小屋の直下に並べていきます。

家の右側の階段と、春に作った森の小道の入り口が見えるようになりました。
視線を向井の山に戻すと、秋の早い夕方が迫ってきています。

驚いたのは無数の立ち枯れ。
あの枯れ木の殆どはアカマツです。
こんなにもたくさん枯れてしまったのか。
春に大発生した毛虫。
松食い虫も大発生したみたい。
輪廻転生で再び新たな木達が育って来るのだろうけれど。
森が死んでいきそうな気がして・・・
これ以上木を切りたくない。